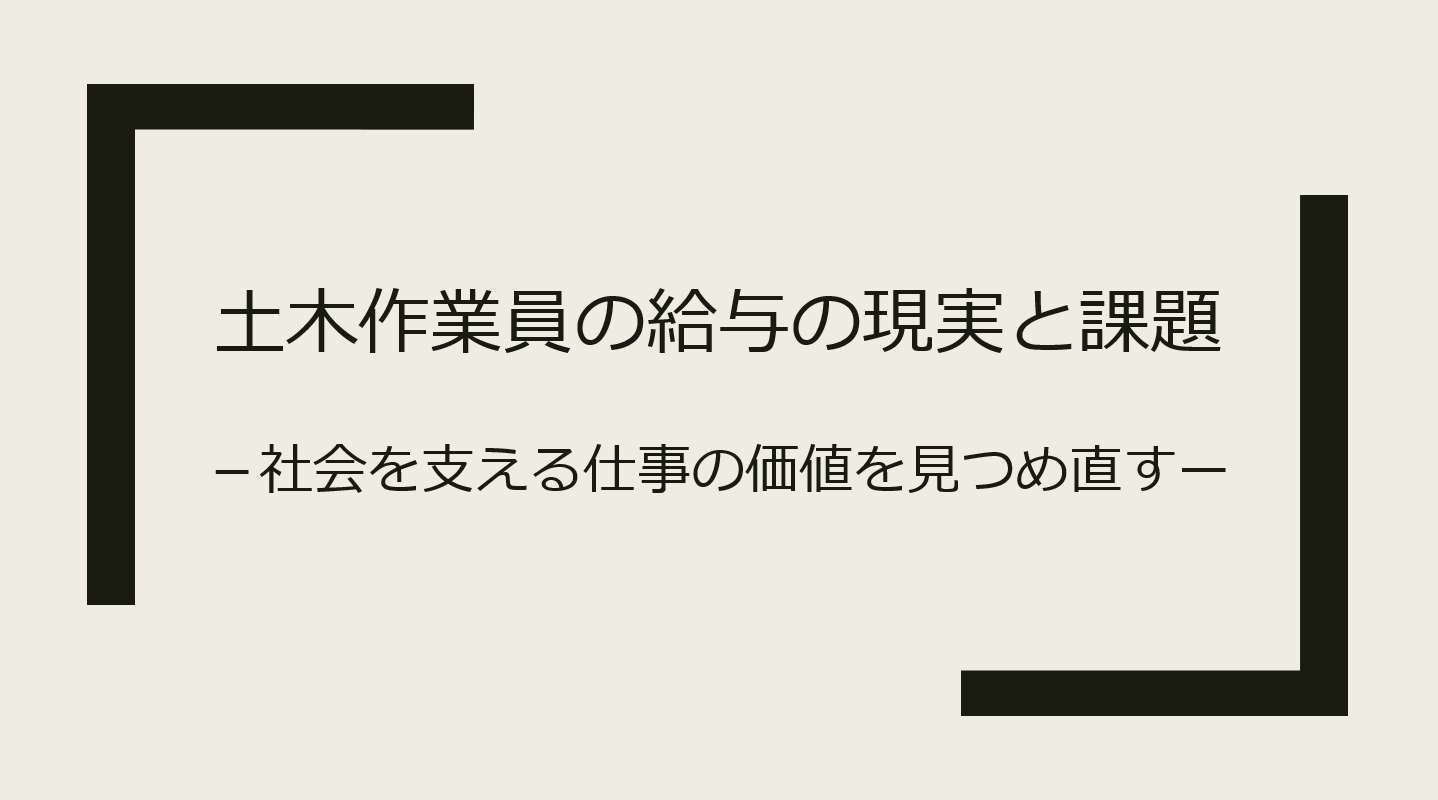皆さん、こんにちは。大阪市内を中心に土木工事や道路工事を中心に行っている互栄土木建設株式会社です。
突然ですが、仕事を探すにあたり重要視することはなんでしょう。自分の好きなこと、休日日数、給与体系、職場の雰囲気・・・人それぞれその判断基準は異なってくることでしょう。そこで本コラムはその中でも給与に関することを解説します。
日本のインフラを支える「土木作業員」。
道路、橋、トンネル、ダム、上下水道といった社会の根幹を担うインフラ整備に従事することは、みなさんの生活に欠かせない存在だと自負しています。しかし、その重要性とは裏腹に、土木作業員の給与や労働条件については、未だに厳しい現実が残されています。
そこで、今回は土木作業員の給与の現状を多角的に見つめ、その背景と課題、そして今後の展望について考えていきたいと思います。
平均給与の実態
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2024年時点)によると、土木作業員の平均月収は約27~30万円、年収ベースでおおよそ350万~400万円程度とされています。ただし、これはあくまで全体の平均であり、経験年数、地域、雇用形態、技能資格の有無、勤め先の規模によっても大きく差が生じます。
たとえば、未経験からアルバイト・日雇いで働き始めた場合、日給は8000円~1万2000円程度が相場になります。月に20日働いたとしても、月収は20万円前後にとどまることが多く、手取り額はさらに少なくなります。一方、現場監督や施工管理技士など、資格を取得し責任ある立場に就くと、年収600万円を超えるケースも珍しくありません。
地域差と季節要因
土木作業の給与には、地域差も顕著に現れます。都市部では公共事業や再開発が活発なこともあり、比較的高めの給与水準が維持されやすい一方で、地方の小規模現場では予算も限られており、人件費も抑えられる傾向にあります。
さらに、天候や季節による変動も無視できません。冬季の降雪や梅雨の長雨などにより現場が止まることも多く、特に日雇いや非正規の作業員にとっては収入が不安定になるリスクが高まります。このような要因が、土木業界全体の人材定着率を下げる一因にもなっているのです。
平日に現場が止まってしまったときには、土日に代替日を設けたりと作業員の収入に極力差異が出ないように取り組むことも会社としての務めです。
給与水準の背景にあるもの
土木作業員の給与水準が相対的に低めに設定されている背景には、いくつかの構造的要因があります。
第一に、下請け構造です。日本の建設業界はピラミッド型の多重下請け構造が根強く残っており、現場で実際に作業する末端の作業員まで十分な報酬が行き届かないことがあります。元請けから下請け、孫請けと仕事が流れるにつれ、中間マージンが差し引かれ、結果として作業員の取り分が減少するのです。
第二に、社会的評価の低さがあります。肉体労働というイメージが強く、いわゆる「3K(きつい、汚い、危険)」の代表例として敬遠されがちな業種でもあります。そのため、若年層の就業希望者が少なく、人手不足が深刻化しているにもかかわらず、待遇改善が後手に回っているという側面があります。
弊社では公共工事の受注にも力を入れているため、元請け企業として工事に携わることも多々あります。また、作業服のデザインやスタイルを工夫したり、安全面には最大限配慮することなど、社会的評価の低さからの脱却も視野に、様々なことに取り組んでいます。
技能と資格により差別化
一方で、技能や資格によって給与を上げていく道も存在します。たとえば、「土木施工管理技士」「建設機械施工技士」「測量士」といった国家資格を取得することで、施工管理や工程管理、安全管理の業務に従事できるようになります。こうした専門性の高いポジションは、年収が500万~700万円、さらに上を目指すことも可能です。
また、技能実習制度により来日している外国人労働者も多く、彼らの待遇や教育も給与水準全体に影響を与えています。今後はこうした人材との共存や、若手の日本人への技能継承も大きな課題となっていくと想定されています。
弊社では資格支援制度も充実させています。各種資格の取得を目指すにあたり、講習費用等はすべて会社が負担します。未経験者でも安心して仕事を覚えられる作業環境な上に、先輩方も優しく指導してくれます。また、それぞれのスキルや努力をしっかりと評価し、認定もしており、取得した資格や現場での活躍はきちんと評価し、給与に反映することによりモチベーションを保ち、やる気も持って働ける環境です。
今後の展望と社会の役割
近年では、建設現場におけるICT(情報通信技術)の導入や機械化の進展により、土木作業の現場も大きく変わりつつあります。ドローン測量、3D施工管理、AIによる工程最適化など、新しい技術に対応できる人材の価値はますます高まると考えられています。従来の「体力勝負」から「知識と技術の融合」へと変わりゆく中で、給与水準にも変化が訪れる可能性も多いにあります。
また、公共工事を発注する行政や、元請け企業の意識改革も重要になるでしょう。価格競争の激化による過度なコストカットではなく、「持続可能なインフラ整備」と「労働環境の改善」を両立することが求められてくることが容易に想像できます。国も「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の普及などを通じて、技能者の処遇改善を後押ししようとしています。
近年、土木作業員の平均給与は上がり続けています。これは作業員だけにいえることではなく、全職種で物価高騰の絡みもあり、上がっています。しかし、そんな中でも建設業界全体は今後も上がり続けるといわれています。その理由は土木だけでなく建設業界の高齢化が顕著に進んでいるからです。高齢化に伴い、若い新人が入り、力をつけることができばいいものの、前述した通り、若手の人材不足が否めない業界です。人手不足が顕著な中でも、インフラ整備や改修工事など仕事が減ることはありません。よって、人材の需要は高いのに供給が足りていないという現状を打破するためにも、労働環境の整備や給与の見直しなどで人材を募集することとなり、結果的に作業員の年収は今後も上がると考えられます。
まとめ
土木作業員の給与は、私たちの社会を文字通り「支える」仕事に見合った水準になっているのか。低賃金・不安定・敬遠されがちというイメージから脱却し、技能と努力が正当に報われる業界へと進化していく必要があります。そのためには、業界の構造的な改革とともに、私たち一人ひとりがその価値を正しく理解することも大切です。
土木作業は、単なる力仕事ではありません。安全・安心な社会の基盤を築く、誇り高いプロフェッショナルの仕事です。その価値が、給与という形でも正当に評価される未来を目指して、社会全体で支えていく必要があるでしょう。
弊社でも微力ながらその一端を担うことができるように、評価基準・給与水準を適正に持ち、土木作業員一人ひとりを大切にしていきます。
どんな仕事をするんだろう、自分に何ができるだろう、疑問があればまずは話だけでも結構です。また、会社見学や現場見学も随時行っております。ご興味のある方は弊社HPよりご連絡頂けますと幸いです。